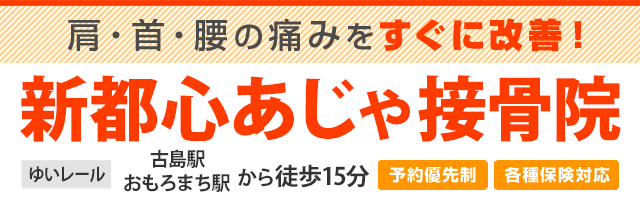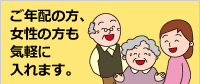肉離れ


こんなお悩みはありませんか?

普段しない動きをしたあと、しばらく動けなくなることがある
過去に運動中のケガ(肉離れ・捻挫など)を経験したことがある
学生時代は激しい運動をしていたが、社会人になってからは運動不足気味
運動後のクールダウンやストレッチをあまりしていない
長時間同じ姿勢や動作を続ける仕事をしている
これらに当てはまる方は、筋肉に負担が蓄積しており、肉離れを起こすリスクが高い状態かもしれません。
肉離れで知っておくべきこと

整骨院で保険が適用される「筋挫傷」の中には、肉離れも含まれます。肉離れとは、筋肉やその周囲を包む筋膜が損傷してしまった状態を指します。
筋挫傷は重症度によって1度から3度に分類され、軽度な筋繊維の伸びが1度、部分的な断裂が2度、完全断裂が3度とされています。
軽度であっても、強い負荷によって筋肉が通常の可動範囲を超えて伸ばされ、組織が損傷しています。そのため痛みは持続し、生活動作に制限が出る場合があります。
受傷後は患部を安静に保ち、固定して修復を促すことが基本です。さらに、血流や代謝を高めることで、回復を早めるための環境を整えることも大切です。
症状の現れ方は?

肉離れは、特に下半身の筋肉で発生しやすい症状です。大腿の前側(大腿四頭筋)や後ろ側(ハムストリングス)、ふくらはぎ(腓腹筋)などに多く見られます。
初期には、動かすと痛い・押すと痛いなどの症状が現れ、重症化すると患部が腫れたり、断裂による凹みが確認できることもあります。
受傷時に「プチッ」という音や衝撃を感じる場合もあり、筋肉痛や疲労と混同してしまうケースも少なくありません。早期に適切な判断と処置を行うことが、回復のカギになります。
その他の原因は?

肉離れは、急な動作による筋肉の伸張だけでなく、
・疲労の蓄積
・筋力低下や拮抗筋とのバランスの乱れ
・柔軟性の低下
・誤った動作フォーム
などの複合的な要因で起こることも多いです。
また、運動前後のウォームアップ・クールダウン不足や、デスクワーク中心の生活による筋肉の硬直もリスクを高めます。
特に、長時間座りっぱなしの姿勢は下半身の筋肉を硬直させ、姿勢の崩れや血流低下を引き起こし、結果的に筋肉を痛めやすい体質を作ってしまいます。
肉離れを放置するとどうなる?

軽度の肉離れであっても、「少し痛いけど動けるから」と放置してしまうと、完治しないまま再発を繰り返す恐れがあります。
受傷直後は、安静・冷却・圧迫・挙上(RICE処置)が基本です。これを怠ると、筋繊維が正しく修復されず、慢性的な痛みや可動域の制限が残ることもあります。
さらに、捻挫と同じように「クセ」がつくと、同じ箇所を繰り返し痛めやすくなり、スポーツだけでなく日常生活にも支障をきたす可能性があります。
当院の施術方法について

当院では、負傷直後の痛みを最小限に抑え、回復を早めるための施術を行います。
まず患部を冷却し、自己治癒力を高める微弱電流(マイクロカレント)を流して腫れや痛みを和らげます。その後、ホワイトテープで適切に固定し、周囲の筋肉を緩めることで血流を促進し、自然回復をサポートします。
数日経過後には、内出血の状態を確認しながら筋力低下を防ぐ施術を行います。また、重心のバランスを整え、再発を防ぐために全身の調整やストレッチ、必要に応じて鍼施術も取り入れています。
回復を早めるためのポイント

肉離れの早期回復には、その場しのぎの処置ではなく、根本的な原因にアプローチすることが大切です。
日頃の姿勢・生活習慣・運動フォーム・水分摂取・栄養状態などを見直し、筋肉にかかる負担を減らすことが再発防止につながります。
当院では、施術と並行してセルフストレッチの指導や姿勢のチェックを行い、患者様ご自身が体の状態を理解できるようサポートいたします。
リハビリを兼ねた通院で、身体のバランスを整え、ケガをする前よりも健康で動きやすい身体を目指しましょう。
監修

新都心あじゃ接骨院 院長
資格:柔道整復師、鍼師、灸師
出身地:北海道稚内市
趣味・特技:お酒、カラオケ