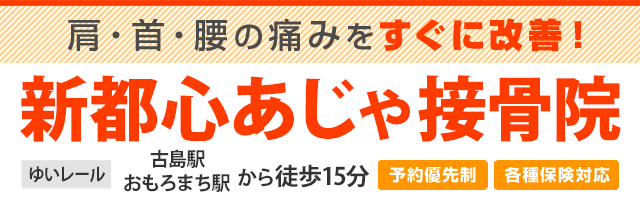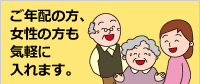顎関節症


顎関節症とは?
みなさんこんにちは、新都心あじゃ接骨院です。
突然ですが、
みなさん美味しく食べられていますか?
または美味しいとしっかり言葉に出せていますか?
もし口が開けにくくて嫌な思いをしたことがある、口をしっかり開けにくいので喋りにくいといったお悩みを抱えている場合、『顎関節症』を疑うべきかもしれません。
顎関節症の根本原因は?
日本歯科医師会によると、一生の間に二人に一人は経験するとさえ言われるほど発症率の高い関節の病で、関節症の状態としては
・顎関節内の上顎と下顎の境目にある「関節円盤」という軟骨のクッションのズレが起き、口の開閉で音が鳴る
・ズレが広がり口が大きく開けられない
・食品の租借時に関節に痛みが出る
といったもので、その原因は嚙み合わせ由来とされていましたが、最近ではそれだけではなく様々な筋肉と顎関節症への負荷が持続してかかり続け、個人の耐久力を超えた際に発症するという「多因子病因説」が採用されているようです。
こんなお悩みはありませんか?

顎関節そのものには痛みなど無いものの、下顎を動かしにくくなる
開口時に頬やこめかみに痛みが出る
といった症状も合わさって、あくびや食事など、日常生活で誰もが当たり前に行う動作や、不意に現れる動作でも悩まされるようになります。そのため、常に緊張した状態になってしまうことがあります。
口の開閉で顎から音が鳴るだけであればそこまで重い症状とは言えませんが、なんと人口の2割もの方々がその症状を抱えていると言われています。物を噛む際に痛みを自覚し整形外科などを受診するまでになると、顎関節症全体の6割にのぼるとされています。これらはかなり身近な関節症と言えるでしょう。このブログをご覧の方やその周りにも、十分にいらっしゃる可能性があります。
顎関節症に対する当院の考え

上にもある通り、顎関節症の発症には、口腔外科や歯科が専門とするかみ合わせだけでなく、多因子による複合的な要因が関係しているとされています。つまり、普段の習慣が顎、側頭部、首といった患部やその周囲に負担をかけ続けることで症状が現れるため、姿勢や身体のバランスといった、整骨院で確認していく領域が関係しているといえるでしょう。
例えば、開口時に引っかかりを感じる右顎側に首が傾いていたり、骨盤が左に寄っているためにバランスを取ろうとして頭を逆に傾けるような姿勢を続けている場合、これは顎関節だけの問題とは言えなくなります。
足首、骨盤、肩の高さ、首の向きなどを左右対称に整えることで、ズレや負担が軽減されることが期待できます。特に重篤な変形がなければ、症状の軽減が見込めるのではないかと考えられます。
顎関節症はなぜ起こるのか?

複合的な要因には、さまざまなものが考えられます。かみ合わせはもちろんのこと、患部に直接強い衝撃がかかる外傷(打撲など)や、不安や落ち込みといった精神的な緊張も影響を与えることがあります。これらの要因により、患部に強い緊張が持続的にかかるため、関節のズレにつながる可能性があります。
よく見られる例として、食事の際に片方の顎だけで噛む癖がある方が挙げられます。また、頬や唇に力がかかり続ける楽器の演奏や、長時間にわたって歌を歌い続けることも、顎にストレスが持続的にかかる要因です。さらに、寝ている際に顎や関節部に腕や枕が圧迫し続ける姿勢も、良くないとされています。
また、持続的にストレスをかける因子として、常に上下の歯が合わさったままになっている「歯列接触癖(TCH)」が問題視されています。特に、顎関節症でお悩みの方の約8割が、このTCHに該当しているとされています。
顎関節症を放っておくとどうなるのか?

顎関節症になると、痛みや関節の動作の異常を恐れ、口を使う動作に常に気を付ける生活が必要になります。口を開けるたびに関節の痛みや衝撃に注意しなければならないため、生きる上で欠かせない食事はもちろん、音楽活動においても制限がかかる可能性があります。その結果、趣味にも影響を及ぼすことが考えられます。楽しく笑うことやあくびをする際にも緊張を感じ、精神的なストレスが蓄積しやすくなるかもしれません。
顎関節症の要因として姿勢が関わっている場合、長期間気づかずに首を傾けていたり、スマートフォンを長時間使用して下を向き続けることで、喉を圧迫するような首の使い方をしている可能性があります。これが原因で、上下の歯が常に合わさっている「歯列接触癖(TCH)」の態になっている場合もあります。また、肥満によって首や顎が圧迫されることで、TCHが引き起こされることも考えられます。
顎関節症は外科的な処置を避けられる場合が多いですが、症状が現れる前から姿勢や習慣に関連する問題を抱えていた可能性があります。
顎関節症に効果的な当院の施術メニューは?

脱臼でもしない限り、口の中を直接触るようなことは整骨院ではできません。しかし、背中が過度に丸くなり、首や顎を前に突き出すような不良姿勢や、片側の肩が上がり、その側に首が傾くことで顎の咬筋に力がかかり続けている場合、姿勢由来の問題と言えるでしょう。
【クリニカル骨格矯正】
首、背中、腰を支える骨盤の傾きを調整して体を支え直し、無理なく頭部を骨で解剖学的な位置で支えられるようにすることで、下からの関節への余計な緊張を軽減することが期待できます。そのために「クリニカル骨格矯正」を試してみるのがおすすめです。
【ドライヘッド矯正】
また、顎関節の動作に関わる内外の翼突筋、側頭筋、咬筋や、頭部の向きに大きな影響を与える胸鎖乳突筋などの筋肉を緩め、正常な位置に誘導する「ドライヘッド矯正」も効果が期待できます。
その施術を受けるとどう楽になるの?

「クリニカル骨格矯正」は、徒手で行う施術で、足首から首にかけての関節を構成する骨の位置関係を調整し、関節を跨ぐ筋肉や靱帯、腱を関節の運動で弛緩させることを目指します。これにより、無理なく体を支えられる状態を作り出します。
解剖学的な状態から大きくズレると、それだけで重力に抗って立つことの負担が増加します。疲れによって頭が前に差し出すような姿勢になりやすく、顎関節が窮屈になっていくのを予防することができます。さらに、緊張で張り詰めた筋肉が動作のたびに痛むことを軽減できることが期待できます。
「ドライヘッド矯正」は、指圧などで直接アプローチすると痛くなりやすい首や顎を弛緩させることを目的としています。手の母指球を使って、頭部から顎の骨格にじっくりと持続的な圧迫をかけて操作します。
ズレて張り詰めた、または窮屈になった顎関節間の筋肉や靱帯が位置を整えることで緩み、口を動かしても痛みが軽減することが期待できます。結果として、通常の大きさまで口を開けられる状態を目指します。
顎関節症を軽減するために必要な施術頻度は?

今まで正常だった顎が、ある日いきなり顎関節症になる例は、事件や事故を除けばあまりないと考えられます。何度も述べているように、多因子による負担の蓄積が徐々に関節を歪めていった結果である場合、何ヶ月、何年もの時間がかかっているはずです。
整骨院では、1年近く時間をかけて施術を行い、初めは週2〜3回の頻度で施術を行いながら、日常生活での異常の確認を繰り返すことを指導しています。症状の軽減が認められた場合は、週1回以上の頻度にシフトし、経過を追っていきます。
その中で、食事の仕方や寝る際の姿勢、睡眠環境などのヒアリングと修正を行います。さらに、首や肩、姿勢維持のための体操の指導といったアフターケアも含め、患者様に寄り添って施術を進めていきます。
監修

新都心あじゃ接骨院 院長
資格:柔道整復師、鍼師、灸師
出身地:北海道稚内市
趣味・特技:お酒、カラオケ