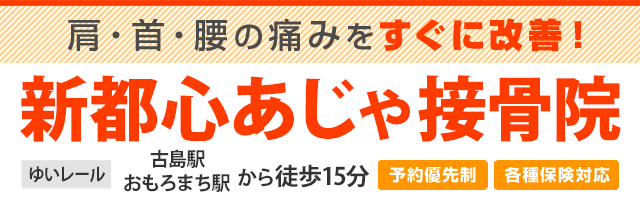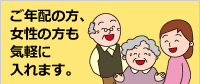オスグッド


こんなお悩みはありませんか?

このような症状が見られる方は、オスグッド病などの膝のトラブルが考えられますので、早めに専門家に相談することをお勧めします。
オスグッドについて知っておくべきこと

膝の皿の下側が上記のように痛む場合、「オスグッド・シュラッター病」の可能性があります。 これは成長期の子供に多く見られる症状で、特に激しく飛んだり全力疾走を繰り返すような競技に取り組んでいる場合に起こることがあります。成長に伴い、骨が伸びる速度に筋肉が追いつかず、その上、筋肉が鍛えられることによって腱や骨の付着部に余計な負担がかかり、運動中に痛みを感じることがあります。 また、身体がもう少し大きくなってから発症した場合、特にバレーボールやバスケットボールなどの競技者に見られることが多いため、この症状は「ジャンパー膝」と呼ばれることもあります。 さらに、長い脚の骨の先端には将来成長するための軟骨がありますが、そこに負担がかかることでオスグッドに似た症状が現れることもあります。この場合、「セーバー病」(踵)や「ケーラー病」(足根骨)などが考えられます。
症状の現れ方は?

運動中に膝蓋骨下に痛みが生じた場合、この傷病を疑うことができますが、診断には画像診断が必要です。具体的には、レントゲンやMRIを使用した検査が行われます。 また、現場での診断には、超音波(エコー)検査が有効です。患部に限局して隆起が見られたり、脛骨粗面部が腱に引っ張られ剥がれている場合、オスグッド病やジャンパー膝が疑われることが強くなります。 痛みによるパフォーマンスの低下が認められ、患部に腫れや発熱などの炎症反応が現れることもあります。 膝を大きく曲げて踵を臀部に近づけるようにストレッチを行うと、症状が引き起こされることがあります。この際、無理に近づけようとすると、体が逃げるように捻じれたり、額を臀部に近づけることで痛みから逃れようとする「尻上がり現象」といった柔軟性の低下が見られることがあります。
その他の原因は?

成長期における体格の変化に加え、クラブ活動などの日常的な動作を超えた動作の反復により、筋肉の付け根や骨の先端にある軟骨部分に症状が現れるのがこれらの骨端症です。特に小学校高学年から高校にかけての年代、特に男子は自身の柔軟性に無頓着であることが多い傾向にあります。激しい運動を行っても、セルフケアをしなくても寝れば治ると考えがちで、そのためストレッチに時間を割かないことが見受けられます。 長く競技を続け、代表メンバーに選ばれると、怪我予防が重要な課題となります。自身でセルフケアを行う必要性を自覚し、その正しい方法を身につけて予防していくことが求められます。 そのため、親や指導者、コーチが適切に導けなかった場合、症状が発生しやすくなることがあります。
オスグッドを放置するとどうなる?

セルフケアを怠り、ひたすら運動を続けると、身体は緊張し、ケガを繰り返しやすくなります。特に社会人よりも若い時期の方が、筋肉がガチガチに固まってしまいがちです。私の経験上、ケガを繰り返す筋肉は瑞々しさに欠け、乾燥した印象を受けます。このように乾いた身体は、容易に壊れやすい傾向があります。 その結果、痛みやその再発に注意しながら運動をしなければならず、運動以外の場面でもケガをするリスクを背負うことになります。安定したパフォーマンスを維持するのは困難になり、部活動などで活躍することが難しくなるかもしれません。さらに、そのまま大人になっても怪我に悩まされる将来を迎える可能性もあります。
当院の施術方法について

オスグットやジャンパー膝になるまで放置された身体では、身体の癖や筋肉による捻れが現れていることがよく見受けられます。酷使された筋肉の過度な緊張に加え、身体の形自体が膝や関節に不要な負担をかけている場合があります。そのため、身体の形を整え、解剖学的に楽な状態に導くことが必要です。 患部だけでなく、その周りの大きな筋肉もストレッチで緩め、骨同士の位置関係を調整してテンションを弱めることが重要です。
改善していく上でのポイント

突然、全身が強く緊張し、唐突にオスグッドに罹る方は非常に稀だと思います。多くの方は、時間をかけて緊張した状態が積み重なり、その結果として診断に至ったのではないでしょうか。そのため、元の状態やそれ以上の良い状態に戻すためには、同じくらいの時間をかけて対応する必要があります。 若いと回復が早いこともありますが、それには休息が不可欠です。部活動を休めない、試合が迫っている、ポジション争いが激しいなど、さまざまな事情があると思います。しかし、回復のためには適切な時間を確保することが重要です。セルフマネジメントをしっかり行い、監督やコーチ、先輩と相談することも、自分自身を守るために必要なことです。 今、何を優先すべきか冷静に考え、回復と予防に時間をかけていきましょう。
監修

新都心あじゃ接骨院 院長
資格:柔道整復師、鍼師、灸師
出身地:北海道稚内市
趣味・特技:お酒、カラオケ